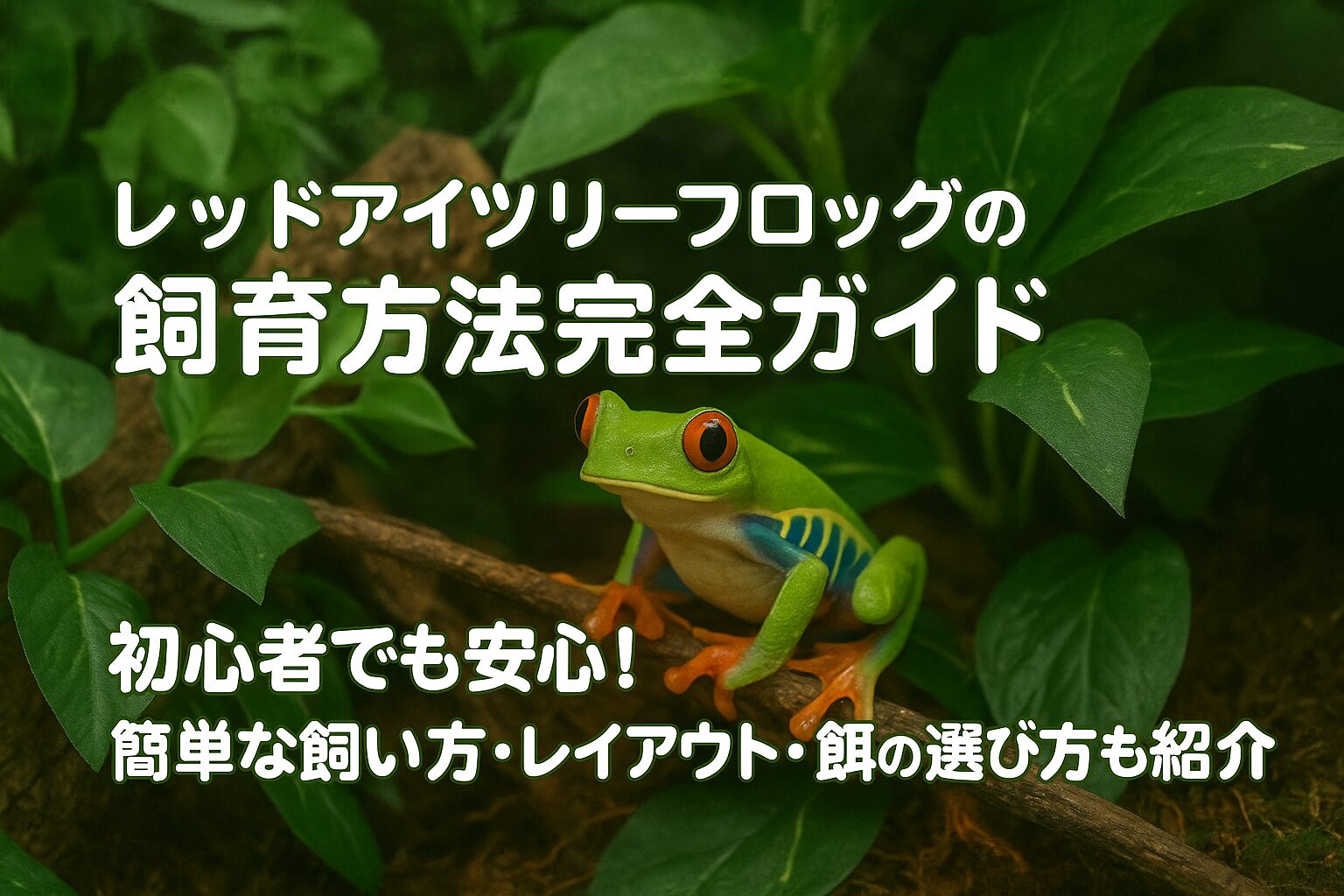レッドアイツリーフロッグは、その鮮やかな赤い目と美しい緑色の体で人気の高いカエルです。飼育方法も比較的簡単なため、初心者でも安心して飼い始めることができます。本記事では、「レッドアイツリーフロッグ」「飼育方法」「おすすめ」をメインに、おたまじゃくしの育て方、餌の種類、ケースの選び方、自作レイアウト、冬の管理方法、そして飼育にかかる費用まで、幅広く詳しく解説していきます。
これからレッドアイツリーフロッグを迎えたい方も、すでに飼育中の方も、ぜひ最後までご覧ください!
レッドアイツリーフロッグってどんなカエル?
レッドアイツリーフロッグ(学名:Agalychnis callidryas)は、中南米(コスタリカ、ニカラグアなど)に生息する樹上性のカエルです。最大の特徴は、その名の通り鮮やかな赤い目と、体の鮮やかな緑色、そして側面に見られる青や黄色の模様です。
夜行性で、日中は葉の裏などでじっと休んで過ごし、夜になると活発に動きます。警戒心は強めですが、慣れてくると愛嬌たっぷりな姿を見せてくれるため、観察する楽しみが尽きません。

▲レッドアイツリーフロッグ(イメージ)|魅力的な赤い目と鮮やかな体色
飼育の魅力と注意点
- 魅力: 鮮やかな見た目、ユニークな動き、夜行性ならではの神秘的な行動観察ができる
- 魅力: 樹上性なので、レイアウト次第で自然なジャングル感を楽しめる
- 注意点: 湿度管理がやや重要(乾燥に弱い)
- 注意点: 大きな声で鳴くこともあり、集合住宅の場合は注意が必要
初心者でもポイントを押さえれば、無理なく飼育を楽しめます。特に湿度管理とケースレイアウトに少し気をつけるだけで、元気に育てることができます!
必要な飼育環境と基本設備
レッドアイツリーフロッグの飼育を始めるにあたって、まず必要なのは「湿度」「温度」「登るスペース」をしっかり整えた環境です。樹上性のカエルであるため、横長より高さのある飼育ケースが理想です。
- ケースサイズ: 目安は幅30cm × 奥行30cm × 高さ45cm以上。1匹なら30×30×45cmで十分ですが、複数飼育する場合はさらに大きいサイズを。
- 湿度管理: 70~80%をキープ。霧吹きでこまめに加湿しましょう。
- 温度管理: 昼間25~28℃、夜間22~25℃が理想的です。
- ライト: 紫外線ライト(UVBライト)は必須ではありませんが、昼夜リズムを作るためにLEDライトを設置すると良いでしょう。
- 登る足場: コルク板、流木、人工植物など、登れる素材を入れてあげましょう。
ポイント:
ケース内に水入れを設置し、カエルが自由に水分補給できる環境を整えてください。水は毎日交換し、清潔を保つことが大切です。
100均グッズでできる!簡単な飼育ケース自作方法
市販の飼育セットを使うのも良いですが、費用を抑えたい場合は100均グッズを活用した自作ケージもおすすめです。
- ケース本体: 100均の大型プラスチック収納ボックス(フタ付き)
- 通気口: フタに細かい穴を開け、虫除け用の金網を貼る
- 登り木: 造花や園芸用支柱を組み合わせて設置
- 床材: ヤシガラマットや水苔を敷き詰める
- 水入れ: 浅めの小皿やタッパーを水場として利用
自作の注意点:
空気の流れを確保するため、通気性には特に注意しましょう。湿度を保ちつつ、カビの発生を防ぐ工夫が必要です。

▲100均グッズで作った簡単なレッドアイツリーフロッグ用飼育ケースのイメージ
おたまじゃくしの成長過程
レッドアイツリーフロッグのおたまじゃくしは、繁殖後に水中で孵化し、数週間~数か月かけて手足が生え、徐々にカエルの姿へと変化していきます。
成長スピードは気温や餌、水質によって異なりますが、約6~10週間で変態を完了するのが一般的です。
変態途中(手足が出始めた頃)は非常にデリケートな時期なので、水深を浅くする・登れる石を置くなどの配慮が必要です。溺れてしまう事故を防ぐためにも、このステップはとても重要です。
必要な水質管理と餌の種類
おたまじゃくしの育成には水質管理が欠かせません。カルキ抜きした水を使用し、週に2~3回は水替えを行って清潔を保ちましょう。
- 水温: 24~26℃程度をキープ(冬場はヒーターが必要)
- フィルター: 強すぎないスポンジフィルターがおすすめ
- 底床: ベアタンク(底なし)または薄めの砂利で掃除しやすく
餌:
おたまじゃくしには以下のような餌が適しています。
- 茹でたほうれん草や小松菜(細かく刻む)
- 金魚・メダカ用の人工飼料(粉末状にする)
- おたまじゃくし専用フード(市販)
ポイント:
餌は1日1~2回、食べ残しが出ない量を与えましょう。水の汚れの原因になるため、食べ残しはこまめに取り除くことが大切です。
成体と幼体で違う?与え方のポイント
レッドアイツリーフロッグの餌の選び方は、成長段階によって変える必要があります。幼体と成体では食べやすいサイズや種類が異なるため、それぞれに適した餌を与えることで健康的に育てられます。
| 段階 | おすすめの餌 | 頻度 |
|---|---|---|
| 幼体(変態直後~3か月) | ピンヘッドコオロギ、ショウジョウバエ | 毎日1~2回 |
| 成体(約4か月~) | コオロギ、デュビア、レッドローチ、ミルワーム(たまに) | 2日に1回 |
いずれの段階でも、餌にはカルシウムパウダーやビタミン剤をまぶすのが推奨されています。特に室内飼育では紫外線不足になりがちなので、カルシウム不足によるクル病を防ぐために必須です。
餌を食べないときの対処法
レッドアイツリーフロッグが餌を食べない原因はいくつか考えられます。
- 気温や湿度が適切でない(寒すぎる・乾燥しすぎている)
- 環境の変化によるストレス(引っ越し直後や掃除後)
- 餌が動かない(コオロギやローチは動きが重要)
- 飽きている・栄養バランスが悪い
対処法としては、以下のような方法が効果的です。
- ケースの温度・湿度を見直す
- 活きの良い餌を与える(ピンセットで揺らすのもOK)
- 餌の種類を変えてみる(動きが違うもの)
- 数日絶食して様子を見る(健康なら大丈夫)
特に新しい環境に慣れるまでの数日は餌を食べないことも多いため、無理に与えず静かに見守ることも大切です。
ケースのサイズ・素材選び
レッドアイツリーフロッグは登ることが得意なカエルです。したがって、ケース選びでは「高さ重視」が鉄則です。
- 1匹飼育の場合: 幅30cm × 奥行30cm × 高さ45cm以上
- 複数飼育の場合: 幅45cm以上、高さ60cm以上推奨
ケースの素材は以下のいずれかがおすすめです。
- ガラス水槽: 見た目がきれいで温度・湿度管理がしやすい
- アクリル水槽: 軽量で加工が簡単(ただし傷がつきやすい)
- 市販の爬虫類用ケース: 通気口・開閉扉付きで便利
注意ポイント:
ケース上部のフタには必ずメッシュ素材を使い、通気性を確保してください。湿度管理とカビ防止のためにとても重要です。
レイアウト例|自然に近い環境を自作するコツ
レッドアイツリーフロッグのレイアウトは、熱帯雨林のイメージで作ると自然な動きが観察でき、カエルもストレスが少なくなります。
基本レイアウト構成はこんな感じです。
- 床材: ヤシガラマットや水苔をたっぷり敷く
- 登り木: コルクボード、流木、大きめの枝など
- 植栽: 造花やリアルな人工植物、または本物の観葉植物
- 水場: 安定感のある浅めの皿に水を常に入れておく
ポイント:
– 登る場所は複数設置して、高さに変化をつける
– 植物はカエルが休める葉っぱの裏側スペースを意識して配置
– 水入れは浅め&出入りしやすい形を選ぶ(溺れ防止)

▲レッドアイツリーフロッグ(イメージ)|自然なジャングル風レイアウトでリラックス
100均の造花や流木を使ってコストを抑えつつ、本格的なレイアウトも十分作ることができます。自作する楽しみもぜひ味わってくださいね。
人気の種類を紹介
「レッドアイツリーフロッグ」と一言で言っても、飼育されている個体には体色や模様にバリエーションがあります。基本的には同じ種(Agalychnis callidryas)ですが、産地や繁殖個体の違いにより、微妙に色味が異なることがあります。
たとえば以下のようなタイプが流通しています。
- コスタリカ産: 一般的なタイプ。グリーンの体に赤い目、青と黄の模様がしっかり出る
- ニカラグア産: コスタリカ産よりやや色が淡く、おとなしい性格の個体が多い
- ブルーバック個体: 背中まで青みがかる個体。特に人気が高く、やや高価
いずれも飼育方法に大きな違いはありませんが、見た目の好みや個性を選ぶ楽しさがあります。
色や模様の違いを楽しもう
レッドアイツリーフロッグの魅力はなんといっても色彩の豊かさです。
| パーツ | 色と特徴 |
|---|---|
| 目 | 赤く大きな瞳。夜間でも目立つ鮮やかさ |
| 体 | 黄緑~濃緑。飼育環境によって微妙に色が変わる |
| 脇腹 | 青と黄色の縞模様。個体差あり |
| 手足 | オレンジ~赤の吸盤付き。吸着力が強く、ガラスも登れる |
写真映えも抜群で、SNSでの人気も高いレッドアイツリーフロッグ。同じ種類でも一匹ずつ違う個性を楽しむのも飼育の醍醐味です。
冬眠はする?させるべき?
レッドアイツリーフロッグは冬眠しないカエルです。中南米の熱帯地域に生息しているため、年間を通じて高温・高湿度な環境を好みます。したがって、冬でも温度を25℃前後に保つ必要があります。
冬眠を試みると体調を崩す原因になるため、絶対にさせないようにしましょう。特に11月~3月は日本の気温が下がるため、ヒーターや保温シートでの温度管理が不可欠です。
冬にかかる費用と暖房設備
冬場の保温対策には電気代や器具のコストがかかりますが、安全に乗り越えるためには投資する価値があります。
- パネルヒーター: 底面に設置して床材全体を温める(約2,000〜3,000円)
- 暖突(上部ヒーター): 空気全体を温める。温度ムラができにくい(約6,000〜8,000円)
- サーモスタット: 設定温度を自動で保ってくれる(約3,000〜5,000円)
- 断熱シートや発泡スチロール: ケースの外側に貼るだけでも保温効果アップ(100均でも可)
電気代はヒーターの種類や使用時間によりますが、月に数百円〜1,000円程度が目安です。保温にかかる費用を最小限に抑えるには、ケース全体の断熱効率を上げるのがポイントです。
冬の環境が不安定だとカエルの食欲が落ちたり、活動量が減ることもあります。「あれ?今日は動かないな…」と感じたら、まず温度と湿度をチェックしましょう。
 |
価格:2000円 |
![]()
初期費用とランニングコスト
レッドアイツリーフロッグを飼育する際にかかる費用は、大きく「初期費用」と「毎月の維持費」に分けられます。ここでは、飼育初心者向けに、ざっくりとした目安を紹介します。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| カエル本体 | 8,000~15,000円(個体・ショップにより変動) |
| 飼育ケース | 5,000~10,000円 |
| 登り木・レイアウト用品 | 3,000~5,000円 |
| 床材(ヤシガラマット、水苔など) | 1,000~2,000円 |
| ヒーター・サーモスタット | 8,000~12,000円 |
| その他(霧吹き、カルキ抜き剤など) | 1,000~2,000円 |
▶合計 初期費用目安: おおよそ26,000~46,000円程度
ランニングコスト(毎月)は以下が目安になります。
- 餌代(コオロギ、デュビアなど)……約1,000~2,000円
- 床材交換代……数か月に1回、1,000円程度
- 電気代(ヒーター・ライト)……月500円~1,500円程度
▶合計 月間維持費: 約2,000~3,500円程度
できるだけコストを抑える工夫
初期費用やランニングコストを抑えたい場合、以下の工夫が効果的です。
- ケースや登り木を100均やホームセンターで調達する
- 餌用コオロギを自家繁殖する(上級者向け)
- 保温効率を高めて電気代を節約する
また、最初から高価な器具を揃えず、段階的にグレードアップしていくスタイルもおすすめです。まずは基本を押さえて、無理のないペースで飼育を楽しみましょう!
ジャパンレプタイルズショー公式サイトの紹介
レッドアイツリーフロッグをはじめとする爬虫類・両生類のイベントとして有名なのが、ジャパンレプタイルズショーです。全国各地で開催され、カエルやトカゲ、ヘビ、昆虫など、さまざまな生き物が集結します。
このイベントでは、ブリーダーからの直接購入や、専門家による飼育講習なども行われており、これから飼育を始めたい初心者にとっても情報収集のチャンスです。実際に生体を見て選べるため、ネット購入に不安がある方にもおすすめです。
▼公式サイトはこちら:
https://www.rep-japan.co.jp/
イベントの開催スケジュールや会場情報は、上記リンクから確認できます。レッドアイツリーフロッグとの運命の出会いがあるかもしれませんよ!
レッドアイツリーフロッグの飼育方法とおすすめポイント総復習
レッドアイツリーフロッグは、その鮮やかな色彩とユニークな習性で多くのファンを魅了する美しいカエルです。特に初心者にも扱いやすく、正しい知識と環境を整えることで、長く楽しく付き合えるパートナーになります。
この記事で紹介したポイントを振り返りましょう:
- 飼育には高さのあるケースと湿度・温度管理が重要
- 100均アイテムでも自作レイアウトが可能
- おたまじゃくしからの育成には水質と餌の管理が鍵
- 餌は成長段階に合わせて種類と頻度を調整
- 見た目や性格に違いのある種類選びも楽しみのひとつ
- 冬の飼育は保温対策が生命線
- 初期費用は約3万円~、ランニングコストは月2~3千円程度
- イベント参加で飼育仲間や生体との出会いも◎
お金をかけなくても、工夫しながら育てていくことは充分可能です。ぜひ、あなたの生活にレッドアイツリーフロッグの癒しと発見をプラスしてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました! 「#レッドアイツリーフロッグ飼育」などのハッシュタグで、あなたの育てているカエルの姿をぜひSNSでシェアしてみてくださいね🐸📷