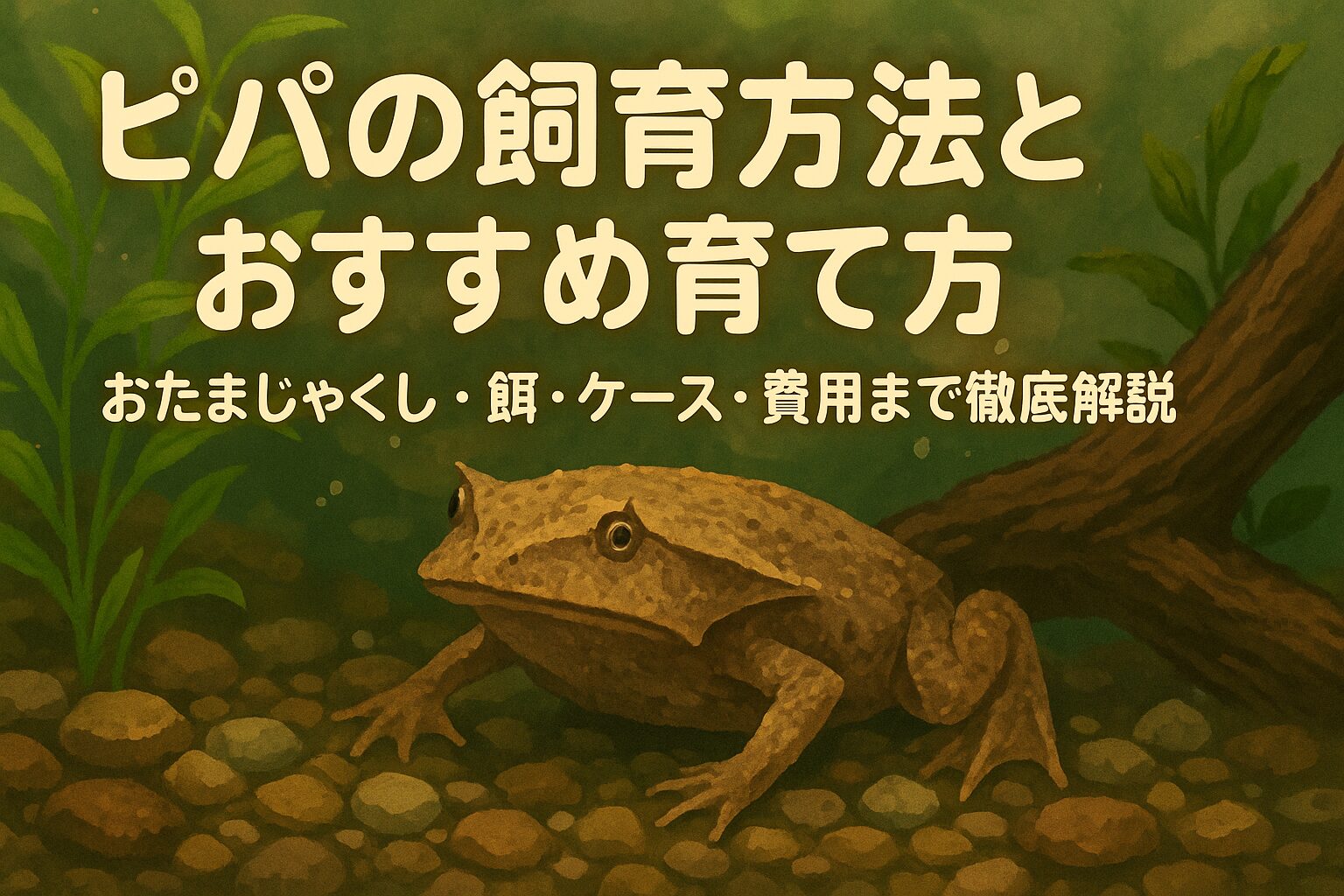ピパの飼育方法を知りたいあなたへ|飼い方・おたまじゃくし・おすすめ情報をまとめて紹介
「ピパってどんなカエル?どうやって飼えばいいの?」「おたまじゃくしの育て方がわからない…」
そんな疑問や不安を抱えている方に向けて、この記事ではピパの飼育方法を初心者目線でやさしく解説します。
ピパ(学名:Pipa)は、水中生活に特化した独特の姿と生態を持つカエルで、見た目のインパクトも大きく、最近じわじわと飼育人気が高まっています。
とはいえ、少し特殊な種類のため、飼い方やおすすめのケース、餌、冬の管理など、事前に知っておくべきポイントがいくつかあります。
この記事では、ピパの基本情報からおたまじゃくしの育成方法、飼育ケースの選び方、費用の目安、さらに100均グッズを使った簡単なレイアウトまで、わかりやすく紹介します。
これからピパを飼ってみたい方にも、すでに飼育中の方にも「なるほど!」と思ってもらえるような内容をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください🐸
ピパとは?種類と特徴を知ろう
ピパは南米の水辺に生息するカエルの仲間で、学名ではPipa属と呼ばれます。中でも「ピパピパ(Pipa pipa)」という種類が最も有名で、平らな体と独特な繁殖方法が注目されています。

▲ピパのイメージ|まるで葉っぱのような平たい体が特徴
ピパの最大の特徴は、扁平(へんぺい)な体型と完全水棲の生活スタイルです。陸に上がることはほとんどなく、水中でのんびりと過ごす姿が魅力です。
また、繁殖の際には背中で卵を育てるという珍しい生態を持っており、観察していてとても興味深いカエルです。
性格はおとなしく、あまり活発に動き回るタイプではありません。そのため、レイアウトに凝るというよりも、飼育環境を安定させることが大切になります。
ピパは「動きが少なくて地味」と感じる方もいるかもしれませんが、独特の生態とマニアックな魅力に惹かれる飼育者が多く、観察重視の飼い方が好きな人に特におすすめの種類です。
ピパの飼育方法とおすすめの環境づくり
ピパは完全水棲のカエルのため、他の両生類とは少し異なる環境を整える必要があります。
ここでは、初心者でも安心してピパを飼えるように、飼育ケースの選び方・レイアウトのコツ・冬の管理まで丁寧に解説します。
飼育ケースの選び方|100均グッズでも自作できる!
ピパの飼育に使うケースは、水をたっぷり張れる水槽タイプ</strongが基本です。
60cmクラスの水槽が理想ですが、45cm水槽でも1匹ならOK。水深は15~20cmを確保しましょう。
最近では、100均グッズを使った自作のフィルターやフタの工夫も人気です。
とくに「水はね防止」や「蒸発対策」にはラップやプラボードが活躍します。
レイアウトのコツ|シンプルで掃除しやすく
ピパは物陰に隠れる習性があるわけではないので、流木や石などは最低限でも問題ありません。
水質悪化を防ぐためにも、底床は薄く敷くか、敷かないという選択肢もあります。
ただし、砂利を使う場合は誤飲しない大きめの粒を選びましょう。人工水草やシェルターも設置すれば見た目が自然になります。
冬の管理|ヒーターとフタでしっかり保温
ピパは熱帯に生息するため、水温は24〜27℃をキープするのが理想です。
冬場は水中ヒーターを使用し、さらに水槽に保温フタをかけることで温度低下を防ぎましょう。
 |
テトラ ミニヒーター コントロール 150W 60cm水槽 60L以下 保温 安全カバー付 サーモスタット+ヒーター一体型 安全機能付 熱帯魚 関東当日便 価格:2660円 |
また、冬眠はさせない飼い方が一般的です。寒さに弱いので、室温が下がる地域では特に注意が必要です。
ピパのおたまじゃくしの育て方と餌の与え方
ピパピパの繁殖方法はとてもユニークで、メスの背中に卵を埋め込み、そこで孵化したおたまじゃくしが自力で水中へと出てきます。
この珍しい繁殖行動を観察できるのも、ピパ飼育の大きな魅力のひとつです。
おたまじゃくしの育成環境
孵化したおたまじゃくしは、親とは別の容器で育てるのが基本です。
20〜30cm程度のプラケースに、カルキ抜き済みの水を張り、弱めのエアレーションを設置すると良いでしょう。
底床は敷かずに、水替えしやすいレイアウトにするのがおすすめです。水質悪化は命に関わるため、毎日〜2日に1回の水替えを目安に管理しましょう。
餌の種類と与え方|成長段階に合わせて
生まれたばかりのおたまじゃくしには、微粉末タイプの熱帯魚用ベビーフードや、茹でたホウレン草の裏ごしなどを与えます。
口のサイズが小さいので、餌はこまかく粉砕して与えましょう。
成長に応じて、赤虫のすりつぶしやメダカの餌なども食べられるようになります。1日2〜3回、食べ残しが出ない量を小分けにして与えるのがコツです。
脱皮と成体への変化
ピパのおたまじゃくしは、前足→後ろ足→尻尾の吸収という順番で変態を進め、約1か月ほどでカエルの姿になります。
この時期は水質変化やストレスに敏感なので、急な水替えや温度変化を避け、落ち着いた環境を整えてあげましょう。
ピパ飼育にかかる費用とおすすめグッズ
「ピパって飼育にどれくらいお金がかかるの?」という疑問を持つ方は多いです。
ここでは、初期費用・ランニングコストの目安と、飼育に便利なおすすめグッズをわかりやすくご紹介します。
ピパ飼育の初期費用の目安
| 項目 | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ピパ本体 | 3,000〜6,000円 | 通販やショップによって価格差あり |
| 水槽(45〜60cm) | 3,000〜5,000円 | 中古や100均応用で節約可能 |
| 水中ヒーター | 2,000〜3,500円 | 冬季は必須 |
| 濾過フィルター | 2,000〜4,000円 | 静音性・メンテ性も要チェック |
| 餌・カルキ抜き | 1,000〜2,000円 | 月々のランニングコスト |
おすすめの飼育グッズ
- エーハイムの水中フィルター:静かで初心者にも扱いやすい定番
- GEXの水温ヒーター:自動調整タイプで温度管理が簡単
- ダイソーのプラケース&ラップ:フタ代用・蒸発防止に活躍
- 人工水草や隠れ家:自然感の演出+ピパが落ち着ける環境に
このように、ピパの飼育は比較的リーズナブルです。
初期費用は1〜2万円程度、月々の維持費は1,000円前後で楽しめるため、費用面でも飼いやすいカエルと言えるでしょう。
ピパの飼育ケースはどう選ぶ?市販品と自作の違い
ピパの飼育環境を整えるうえで、最も重要なのが「飼育ケースの選定」です。
ここでは、市販ケースの特徴と、自作ケースの工夫例を比較しながら、それぞれの良さを紹介します。
市販品のメリット・デメリット
市販の水槽や飼育ケースは、安心感・耐久性・水漏れ対策の面で非常に優れています。
ガラス製やアクリル製、プラスチック製など多様なタイプがあり、ピパの大きさや数に応じて最適なサイズを選べます。
ただし、価格がやや高めだったり、レイアウトが固定されていて融通が利かないこともあります。スペースや予算とのバランスを考えて選びましょう。
自作ケースの工夫とポイント
100均やホームセンターで手に入る収納ボックス・プラケース・すのこなどを使えば、低コストで自作ケースを作ることも可能です。
たとえば、透明の衣装ケースを水槽として活用し、フタはラップやアクリル板で自作すれば、ピパの水跳ねも防げて保温対策にもなります。
ただし、自作の場合は強度や水漏れのリスクがあるため、水を入れる前に必ずテストを行い、安全性を確認してから使いましょう。
おすすめの選び方
1匹だけを飼育するなら、市販の45〜60cm水槽が最も安心です。
複数匹を飼う予定がある方や、費用を抑えたい方は大きめの自作ケースにチャレンジするのも良い選択です。
どちらにしても、フタの有無・水深の確保・掃除のしやすさはピパの健康を保つうえで非常に重要な要素です。
ピパの飼育方法とおすすめポイントをおさらい
ここまで、ピパの飼育方法について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたか?
ユニークな見た目と生態を持つピパは、完全水棲で飼いやすく、おすすめのカエルです。
おたまじゃくしの育成から餌の与え方、ケースの選び方や自作の工夫、冬の管理方法まで、初心者でも無理なく始められる情報をお届けしました。
費用も比較的リーズナブルで、100均グッズや簡単なレイアウトでも十分に楽しめます。
「ピパを飼ってみたいけど不安…」という方も、まずは小さなケースから始めてみるのがおすすめです。
冬眠させずに水温管理を意識することで、1年を通して元気に育てられます。
もし、この記事を読んで「ピパって面白そう!」「こんなカエルなら飼ってみたい!」と感じたら、ぜひ一歩踏み出してみてください。
あなたの暮らしに、新しい癒しと発見を与えてくれる存在になるかもしれません🐸
🔗 ジャパンレプタイルズショー公式サイトはこちら
※イベント会場では、ピパを実際に見たり、飼育相談もできることがあります!